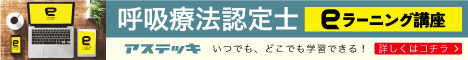時差投稿になります
いつも訪れて下さってありがとうございます𖤣ᐝ
初めましての方にも読みやすいように過去の記事を掲載します
もしくは、リンク集の中をご閲覧ください
私について↓
2021年11月4日
病院受診日

昨夜は
痛みに眠気が勝って眠ることができた。
今朝のコンディションも悪くはない
朝食を食べてゆっくり準備して
わりと余裕を持って出発
12時半ごろ病院到着
13時予約
14時ころ診察室へ
15時終了
今月で、先生のところに来て約1年が経つことと感謝の気持ちを伝えた。
「1年前、あのまま前の病院に通院していても治せない」と自分で気づいた。そう思って即行動に出たときに、頼る人・頼れる人がいて本当に良かった と伝えた。
気づいても、頼れる医師や病院が無ければ途方に暮れていたかもしれない。今こうして頑張れている環境や、関わってくれている方々がいることは本当に貴重だと感じている。
『 ありがとう 』と振り返って先生に話をしたら、先生が「県内で車椅子スポーツを推奨したり活動したりしている人がいて、僕のところにも通院で来ているんだよね。年齢はoliよりもかなり上で、車椅子歴も長いけれど。そしてその人と、車イスの30代の患者さんを繋いだら、良い影響を受けて障害者スポーツにも興味を持って… ちょうど今日来てるんだけど、会ってみる?」と言ってくれた。
私は何の迷いもなく
「はい、会いたいです」と言った。
初対面。
その方の情報としてゆりさん という仮名で綴る
◆事故後→ 全身の痛みを抱えている
◆車椅子歴30年
◆初対面で キリスト教だと宗教の宣言
◆精神疾患や障害を持つ方のカウンセリングを行なっている
◆過去に障害者スポーツ選手であった
◆作品展にて数々の作品で入賞(手も痛みがある)
◆車椅子の方がつどえる機会をつくっている
旅行やレクリエーションなども企画
◆学生時代はスポーツに取り組みインターハイ出場経験あり
◆SNS等はなく、電話やショートメールでのやりとりをご希望である
ゆりさんに出会った30代の方が窓口になって、車椅子連合会を立ち上げる予定?などの話も伺った。この辺りは曖昧なのでハテナをつける。
偶然にも住まいが隣の市だったので、通院はどうやっているんですか?と聞くと
バスを乗り継いで来ている、と。
驚いた(笑)
普段はお住まいの地域の病院の疼痛外来に通院していて、メインは私と同じ主治医なのだそう。
なんだか不思議なのだけれど、私の主治医が持つ力が以前よりもっと分かった気がした。
どんな症状で車椅子になったの?から始まって、病気の話を詳しくはしなかったけれど、
「今どんなことをしているんですか?」という質問を、早い段階で投げかけてもらったことにとても驚いた。
●今こんなことをしている
●これが目標
●勉強中のこと
簡潔にお話した。
けれど、
この質問に答えられる闘病中の方って
どのくらいいるんだろうと思った。
初対面の質問にしては驚いた。
慢性疼痛という大きなくくりの中で、
痛みと共存しているということは
「いつもつらいし、いつも問題を多く抱えて生きている」
強い痛みがない障害や病気で「一生歩けません」「一生車イスです」というケースは多々ある。私が知らない病気も障害もたくさんあると思う。
もし『痛みが無ければ』と考えると
たとえADLに限度があったとしても
アクティブに外の世界と繋がることは
できるかもしれない。
…
もちろん病気の辛さは比べられないし
人それぞれ何かと闘って生きている。
これが前提。
けれど
ずっと痛みある人の気持ちが分かるから、活動や今取り組んでいる等の内容は、外の世界と不自由なく繋がっている方同様にはならないケースもあるのではないかと思った。これは最近の気づき。
結局うまく文章を繋げる言葉が思いつかなかったのだけれど、伝えたかったのは、初対面での問いかけにしては大胆だったこと。
いきなりこの質問をしても大丈夫な人よりも、「痛みはどう?」というように、当たり障りないような質問が初対面では一般的だと思う。ということ。
きっと主治医がゆりさんにoliの紹介をしたときにoliはこんな事をしていてこんな人と簡単に説明してくれたのかもしれない。
前置きがあったから
そんな質問が
会話の初めに出てきたんだなぁと思う
それがあっての会話だった、と。
______________________________
私が簡潔に今の取り組みなどを話すと、ゆりさんも、障害を負ってからどんなことをしているか教えてくれた。
連絡先を交換し、今月中旬にイベントがあるからもし良かったら来てくださいねと教えてくれた。
ゆりさんは最後に、下記のような言葉をくれた。
痛かったら泣いていいし
叫んでいい。
痛いからって感情を我慢しなくていい
我慢すると精神的な影響が強くなるから
吐き出していける場があることも
溜め込まないことも、
願いだ と。
確かにおっしゃる通り。
最後に握手をして、ゆりさんは処置室の方へ
私は診察室へ戻った。
握手が左手だったのは右手は痛みが強いからだと分かる。左手だって痛いのに握手を求めてくれて。この手も痛いでしょう と言ったらゆりさんの手が緩んだのが分かった。

行動している人や
想いある人はたくさん知っているけれど、
実際に会うと違う。
ものすごく強い。
車椅子っていうだけで弱者に見えるのに、
相手の中身を知ると見た目とは異なる『強さ』を感じ取れる。
弱さは時に強さに変わる時もある
患者の悩みというのは多岐に渡り、
車イスユーザーの悩みもたくさんある。
コンタクトを取って話す場を作るのも、精神的フォローという面でゆりさんがやってきたことなんだなと思った。
人と話すのが好きな自分にとって
直接人と関われる事はとても良い影響となった。
先生、ゆりさんありがとうございます。
そして診察。。。
主治医との話
①生活について
②現状の共有
③悩み相談
④薬の処方について
⑤先生の想い
①〜④については記録の通り
記録として記載
(★こちらについては細かいので
記録に関心のある方はご覧下さい)


⑤集学的治療について
先生は、わりとなんでも自分でやりたい人だと言う。
他科との連携などは、面倒と思う方(ほう)。
でも
自分でできる限りはやりたい。という。
集学的治療を地元でもできるようにしたい
という思いは熱いものが感じられる。
痛みに特化したスタッフを集めて
治療体制を作りたい、と。
いつになるかわからないから長い目で見ていてほしい。と言うものの、集学的痛みセンターの存在意義・存在価値は私自身も学び、体感しているので何か協力できたら嬉しいと思っている。
私の場合診察は、毎回 自分で1ヶ月を振り返ってまとめておき、それを共有したり、気になった事や悩みを話したりするというもの。(私が自然とその流れを作ったかもしれない。まとめてきて共有するのは勝手に始めたから(笑))身体のことや痛みを共有したり、新たな試みを話したりする時間はとても大切だと感じている。
時には先生が勉強してくれて学んだことを教えてくれるし、私も新たなリハビリ方法が思いついて先生を頼りたい時は相談する。目的を持って先生に伝えるから、「それいいね!」とか「素晴らしい」なんて言って手助けしてくれる。有り難い。
今回は、右外側大腿皮神経痛の激痛は無かったので、ブロックは無しで診察終了。

慢性疼痛医療について思うこと
1つ前の病院は主治医が整形外科医。
だからリハビリのオーダーもしてもらえたのだけれど。(リハビリについては本当に感謝している。過去の記事でも書いたが、私は当時の主治医のスタンスが合わなかったのでそれがストレスだった。)整形外科医に対して、慢性疼痛治療の全てを担うことは、要求し難いように思うこの頃。※
つまり、患者側が求めても困ることになるし、
医師側も求められても困るということが
実際問題あり得ると思うようになった。
整形外科医で、『目の前の患者が困っていることを理解する』という目標を一人で達成すること は無理。
無理があっても仕方ないなと考えるようになっている。
しかも、他職種との連携を取りやすい環境・人間関係を構築していなければ、患者を診るなんて到底言えないと思う。整形外科は広範囲に及ぶ運動器官を対象としている。痛みを抱えている故の精神的な苦悩や、脳の機能低下についてはサポートしきれない。
あくまでも整形「外科」。得意とする専門は、スポーツ外傷とか肩、腰、手、脊椎、足、もうたくさんあるけれど。
四六時中痛みがあることによって睡眠不足になっていれば、精神科医が睡眠には詳しいからコンサルトするし、食べ物を食べられない状態であればもちろん他科を頼る。目に見えることや患者の「眠れない」というサインには対応できると思う。
集学的痛みセンターで学んだことなのだけれど、多面的に診て、個々人の問題点を見つけることができないと治療の方向性が決まらないし、進まない。複雑な問題を抱えていることも充分にあるし、皆んな葛藤している。
ひとりだけでは患者の理解に追いつかないと思う。
だから、
一緒に頑張っていきましょう
もしくは
1つずつやっていきましょう
などという言葉が(医師から)
自然には出てこないと思う。
他の診療科も言ってみればそうだと思うけれど、慢性疼痛患者が通るのは整形外科・ペインクリック(麻酔科)・神経内科・脳神経外科あたりが多いから、ここでは自身の経験した「整形外科」を例に挙げた。
※集学的治療を行なっている病院は例外
整形外科医が主治医で、看護師や臨床心理士、リハビリ職、精神科医、神経内科医、社会福祉士、管理栄養士など様々な視点を持つ方々が集まってひとりの患者を診ることができる。
チームのようなイメージ。主治医の専門科が麻酔科医でも神経外科医でも、同様。精神科の医師で、慢性疼痛医療に携わってご尽力されている方も知っている。
慢性疼痛医療が他国に及ばないのは
コミニュティーの問題もあるけれど、
こういう場合どうすればいいの?
って、医療従事者も分かっていないというのもあると思う…
(↑冒頭で書いたように、攻めるわけでもないし、仕方ないこともあるし、文句として書いているわけではないことをご理解ください。)
整形外科だと、例えばオペ後に残存する痛みなどに関しては
「リハビリすれば治るから」
「少しずつ無くなっていくから」
と、片付けてしまいがちだと思う。
「声」を聞かずに判断する
または
器質的な問題が見つからなければ
精神科医へ紹介する とか。
あるあるなんだよなぁ…
【疼痛医療に携わる医師に伝えたいこと】
ますますの発展・目の前の一患者を良い方向に進んでいただくために必要なのはきっと、患者や病気を治した(または寛解した)人の声だとも思っております。ペインの先生たちやセラピストの方たちが頑張ってくださって、この数年でようやく研修会や症例検討会が盛んになってきているのではないでしょうか?慢性疼痛という理解は進みつつあります。
でも、その垣根を越えることも必要と思っています。社会的には理解されにくい多くの難治性疼痛や慢性疼痛の患者が感じる痛みや苦悩。それも貴重な声だと思います。
ですがそれだけが声となるのではなくて、これをやったら良くなったとか、生活の中でこれを試したとか…そのような人の声は貴重で有益な情報です。
診察時間は限られていますし、1人の患者に割ける時間も少ないと思います。私の主治医は、診察時間を学びの場と捉えて下さっていると感じています。様々な症状がある私の身体のことすべてを説明できる医師はいません。
医療関係者の皆さんの症例検討会や論文発表以外にも、患者の力や、病を克服した方の力というのは侮れません。私は、主観ですが患者側もすごく力を持っていると思います。臨床で見る患者の理解につながる方法や、アプローチ方法が多く集まると良いと常々思っています。
医師やセラピストの「困ったなぁ。どうしたらいいものか」というお悩みを解決するためにも、引き出しのレパートリーを増やすべく、患者を頼ってください。私のような患者も頼ってください。通常は「頼られる側」だと思いますので、時には頼ってください。
医療に携わる皆様のために協力してくれる方は多いはず、と私は信じています。
以上です
____________________________________________________________
医師の気持ちも患者の気持ちも分かるようになった今、架け橋になりたいという想いは変わりません。
1人でも多くの方が適切な医療を受けてほしいし、受けられる体制が必要だし、社会的な側面でも「他者に理解してもらえる」ような日本にしたいという想いは変わりません。大きすぎる目標ですが。
医療に関すること、制度などの事は医療事務資格を取るために勉強したのですが、次は心理面での勉強を始めました。
今は準備期間。未来への投資時間。
そう思ってリハビリやADL向上のために頑張ります
◆━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎◆
尽力されている多くの方々に
明るい光が見えますように…
◆━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎◆
長くなりましたが、最後まで読んで下さって
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ありがとうございました
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
run tomorrow
明日を動かせ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
:▷▷SNS もよろしくお願いします:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
https://www.instagram.com/nuku_reproject/
▶︎NUKU