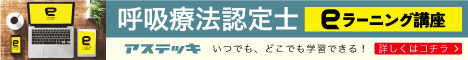ブログをご覧いただきありがとうございます
私はCRPSという病気と闘う記録を残しながら、同じように苦しむ方が1人でも少なくなるように支援してゆけることを目指し、過ごしています。
今回は
①理由が見つからない激痛
②精神的なフォローの必要性
③記録
という内容で構成しました。
最後まで読んで頂けると幸いです。
◆理由が見つからない激痛◆
私は過去のCRPS経験上、怪我の後の痛みや症状はCRPSだとすでに自分で判ったので受容はスムーズだった。何でまた自分が…なんで2度も…と沢山泣いたけれど。
一度経験していたから、こうなだけであって、
診断がつかずに困っている人はたくさんいるんだなと、色んな方からご相談をいただいて気づかされた。
今の時代は、ネットで調べたら
慢性疼痛の中でもトップな痛みのCRPSだから
症状と照らし合わせて
もしかして?と思う事はできるかもしれない。
自分の主治医が知らずとも、一般の方のほうが検索しまくることはできる。
でも
一通り検査を行わない段階で
すでに
疾患の病態に当てはめてしまう
そう、「自分はCRPSなんじゃないか」
「絶対にCRPSだと思うのだけど
どう?」というふうに。
こうこうこういう症状がある。
日に日に悪くなっていく
歩けなくなるんですか?
などなど。。。
焦りや不安から、ヘルプのメッセージが度々届く。
何でも決めつけてしまう
というのは良いことでは無いと感じている。
CRPSでよかった〜なんて思える?それは違う。
でも、それでも私はヘルプを受け止めてきた。
これからも自分にできる範囲で受け止めるつもり。
病名がつかない不安や、病名がつかない事による弊害は大きいと思うから。
どれだけの不安を抱えているか
想像できるから。。。
医師にしか判断できないことは当然私は判断できないし、診断するのは医師。だからお伝えできることは、様々な事に配慮しながら伝えさせていただいている。確信をつけない部分はご理解いただきたい。
ペインの医師は患者の状態を見て、精査をすると病気が分かる事が多いので、時には患者自身の見解にこだわらず、医師の意見も受け入れる事も必要だと思っている。
今の私からみて、伝えたいのは
今できることに目を向けてほしい
ということ。

伝え方が大事だなと常々思うので、自分の立場をわきまえつつこの事の重要性も伝えられるように努め、これからも勉強していくつもり。
◆精神的なフォローは必要だと思う◆
というのも、最後まで読んでいただきたいのは、検査で何もないから次は「精神科で診てもらってください」という事ではありません。
治療のフォローとして精神科医が診療するか
疼痛外来の医師が心のケアもするのか
臨床心理士や認定心理師がフォローしていくのか
カテゴリーが異なるだけで、
私は
身体に強い痛みが続く場合、
精神的なフォローは必要だと思うようになった。
自身は、臨床心理士や認定看護師のサポートを受けていた時期もある。サポートといっても、別にアドバイスがあるわけではなくて、状態を「話す」ことだけれど。
話す中で、新たな気づきが生まれたり
自分では気づけていなかったことに
ようやく気づけたり…
とにかく気持ちを表出できた時は
良いことしかなかった。
不安は消えることはない。けれども
つっかえていた感情や出来事に
明かりが差すというイメージ。
当時の医師に対する愚痴を聞いてもらったり、「私はこう考えているのだけど先生の考えが分からないので知りたい」と伝えたりして仲介役になってもらった時もあった。
簡単に気持ちを打ち明けられなかったり、何が苦しいのか分からなくなっている時は、素直に
分からない・表現ができない、と伝えていた。苦しいことなんてもうたくさんありすぎて辛い。と。「痛くても歩け」「左下肢に力が入りづらくて、膝折れしようとも歩け」という医師の意図がわからない
と、過去には思ったままの事を打ち明けた。
打ち明けさせてもらったことに
すごく感謝している。
車椅子で自由に外出できるようになったら
会いに行きたい
誰かに表出するのも大事だし、そんな機会を痛みと常に付き合っている方にも設けられることが望ましいのではないかと私は思う。
↑
個人の選択を尊重した上での話。
今の私のように、心理士さんや認定看護師などの存在が不要な環境であれば無理に求めることは
もちろん、ない。
そして
苦しさを言葉にできないから
日記(記録)をつけていたことで
ノートには正直な自分や、その時に闘っていた感情を
振り返ることができた。
病気になったら
ノートやスマホ、媒体はなんでもいいから
記録をつける事もおすすめしたい。
いつか役に立つから。私は10年前に闘病していた時に書いていた『リハビリノート』数冊が本当に役に立った。気持ちを救ってくれて、過去の自分から励まされた。
どこも病気じゃなくて健康体でも
日記をつけている方はいる。
目的は様々あると思うけれど、
後から日記を振り返ると、その時の自分と今の自分の変化に気づくこともできる。
日記のデメリットを見つけるより
メリットのほうが多いと考えている。
ただでさえ社会的に理解が得られづらい病気で、医療従事者も知らない場合が多い病気。

どういう状態で、今一番苦しいことは何なのかというのを「患者を診る側」が理解しようとしてあげなければ、治療方針が決まらない(定まらない)。
CRPSは心の病気が発端になるわけではなくて(一部の要因として心理的要素がある場合もある)、激痛と共に過ごすが故に精神的にも影響が出るという仕組みが大半だと思っている。
これは当然のことのようにも思う。
さすがの鉄人メンタルを持ってしても、
この痛みを味わったら絶望感を感じると思うし
受け入れ難いと分かるはず。
でも、その過程すら理解しようとしない医師がいるから「精神科へ行ってください」という補足なしのストレートな言葉、安易な言葉が出る現場が未だにあるのだと思う。
強い痛みに耐え続けるという日々を長く経験して、その影響で精神的に辛くなって当然。その精神面をフォローできる役割が必要。
精神的なフォローが必要。
↑
でもその理由って、
「心が病んでいるから」という理由ではなく、
「痛みと付き合っている分、精神面でも辛いと思うから何らかのアプローチをしましょう」という理由の方が望ましいのではないだろうか。
伝え方と、伝わり方は違う。
______________________________
治療の計画を立てるのは、
医療者と患者両方が同じ方向を見るところから始まるのではないでしょうか?
だからこそ患者の状態をちゃんと知ってもらう必要があるし、知るまで視野を広げて、様々な可能性も試して知ろうとしてほしい。
大抵の病院には主治医1人ではなく頼れる医療職がいるわけだから協力してアプローチ法を考えられることを強く願いたい。
患者である私も、
伝えることをあきらめないで
周りの人達との関係を築いていきたいと思う。
______________________________
追伸)メッセージ

心理的なサポートのことや日記のことが
困っている、苦しんでいる誰かの参考になれば幸いです
______________________________
資格がなくてもできることかもしれない
型にこだわることはないのかもしれない
と、色んな可能性を見ているところです
run tomorrow
明日を動かせ
◆記録抜粋◆
2021年11月24日
みぞおちの筋肉痛?がある。
肋骨・肺・呼吸 関係しているのかも
午前中左足に装具(オルトップ)着用。
オルトップ=短下肢装具
オルトップは
2019/10 左足の腓骨神経麻痺の疑いで
治療用装具として作成していたもの。
最近立つための訓練をPTさんと始めた際に左足首の関節の拘縮が気になっていたので、自分の手で動かすだけではなく、装具着用にて悪化を防ごうという取り組みを始めた。
右足の親指の爪切りチャレンジはクリア
爪を切るのも痛みに繋がる、アロディニアという症状がある。
ほぼ1日、左足には靴下を履いて過ごした
〈現状の補足〉
□右下肢はCRPSの特有の症状・疼痛が残存
アロディニアにより、
靴下や靴を現在は履くことができていない
(2018/11 発症 〜 2019/4〜6 リハビリにより靴を履くことや1km歩行が可能まで回復に。その後は悪化を辿っていた。しかし2021/9頃〜床に足を着くことが可能になり少しずつADLも向上している)
□右外側大腿皮神経痛
□左下肢は麻痺がある状態(CRPS)
随意的に動かすことは困難
リハビリやイメージトレーニングにより、少し反応が見られるようになってきた
最後まで読んで下さってありがとうございました
いつも貴重な時間をかけて読んで下さる皆さま
応援して下さる皆さま、
本当にありがとうございます
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
:▷▷ SNSもよろしくお願いします:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
https://www.instagram.com/nuku_reproject/
▶︎NUKU All information